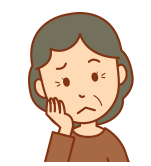
「ダイエットでカロリー計算は大事っていうけど、どうやって計算すればいいのかしら…」

「この食事量はダイエットに適切なのかな? 摂取カロリーが多すぎるのかの判断がイマイチ分からない…」
上記のような悩みを持った状態でダイエットに取り組んでいる方は多いのではないでしょうか。
ダイエットを始めると、最初にぶつかる壁、それが「カロリー計算」です。
もしかしたら、カロリー計算って面倒だし、難しいと思っているかもしれません。

しかしながら、カロリー計算を適当に行うorやらないという選択肢を取ってしまうと、ダイエットに再現性がなくなってしまいます。
また、それだけでなく、一時的に痩せたとしてもすぐにリバウンドしてしまうような事になりがちです。
実際のところ、2回目のダイエットというのは、一回目のダイエットよりもうまくいかないケースが大半であり、ダイエットを行ったつもりが脂肪とストレスを蓄えただけのような最悪なケースに陥りがちです。
だからこそ今回の記事では、カロリー計算を簡単に理解し実践する方法をお伝えします。さらに、それを実生活にどう活かすかをステップバイステップで解説します。
無駄な食事制限や過度な運動を避け、理想の体型を目指すためには、カロリー計算こそが最短の道です。
この記事を読めば、今まで感じていた「カロリー計算の難しさ」や「食事管理の不安」がなくなり、自信を持ってダイエットを続けることができるようになるでしょう。

あなたにぴったりのカロリー計算方法で、理想の体型を手に入れる第一歩を踏み出しましょう!
また、現在ですが新規の方限定でこのサイトの管理人であるtakutoがダイエットの無料カウンセリングを行っております。
現状の状況をヒアリングしてから、おすすめの食事ペースや摂取カロリーの目安、どの運動がおすすめなのかをオンラインでアドバイスしていくものです。
このカウンセリングは今までダイエットに失敗してきた人はもちろんですが、以下のような人にもおすすめです。
- どんなダイエットを進めていけばいいのか分からない人
- どんな運動をすればいいのか分からない人
- 今後、二度と体型で悩みたくない人
- 好きなものを食べても太らない体を作りたい人
上記に1つでも当てはまる方は、ぜひ気軽に検討してみてください。

それでは、ダイエット成功者が利用しているカロリー計算について詳しく解説していくので、ぜひ参考にしてください!
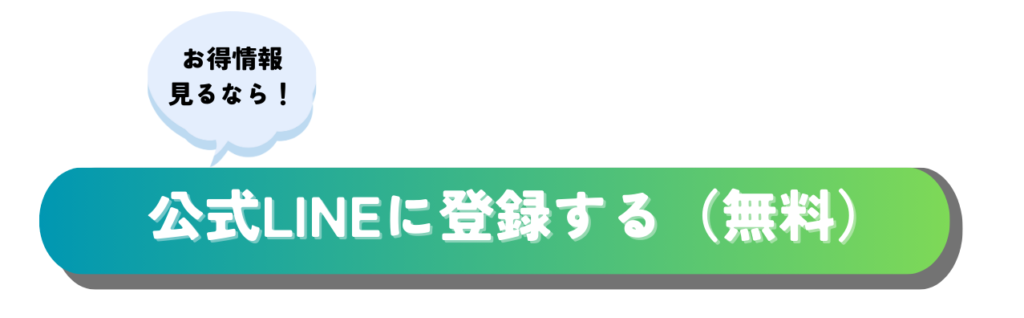
※過去に自身が担当させていただいた他社のお客様・他社の会員様は対象外です。新規のお客様限定のサービスとなりますので、あらかじめご了承くださいませ。また、こちらはパーソナルトレーニングの勧誘を目的としたものではありません。
ダイエットを成功させるためには、まず「摂取カロリー」と「消費カロリー」の関係を正しく理解することが大切です。
食べたものがどれくらいのエネルギーになるのか、そして体がどれくらいエネルギーを使っているのかを知ることで、効率よく健康的に痩せることができます。

また、自分の適正体重を知ることも、目標を決めるうえで役立ちます。
本記事では、ダイエットの基本となる「摂取カロリーとは何か」「消費カロリーとの関係」「適正体重の計算方法」についてわかりやすく解説します。
摂取カロリーとは、食べ物や飲み物から体に取り込まれるエネルギーのことです。
私たちの体は、食べたものをエネルギーに変えて動いています。
例えば、ごはん1杯(150g)には約250キロカロリーのエネルギーが含まれています。
このエネルギーが人間の体を動かす燃料となります。
農林水産省によると、1日に必要なエネルギー量は、成人女性で約1,800~2,200kcal、成人男性で約2,200~2,600kcalとされています。※1
※1:農林水産省:(一日に必要なエネルギー量と摂取の目安)
摂取カロリーは「おこづかい」に似ています。
食べ物からもらうエネルギーが「おこづかい」、体が使うエネルギーが「使うお金」です。
おこづかいが多すぎて使いきれないと、余ったお金(=脂肪)が貯金されてしまいます。

摂取カロリーを適切に管理しないと、必要以上にエネルギーが体に蓄えられ、太る原因になるので注意してくださいね!
ダイエットの基本は、「消費カロリーを摂取カロリーより多くすること」です。
体は食べたカロリーよりも多くのエネルギーを使うと、足りない分を体に蓄えた脂肪から補います。
その結果、脂肪が減って体重が落ちるのです。
厚生労働省のデータによると、体脂肪を1kg減らすには約7,200キロカロリーを消費する必要があります。※2
※2:厚生労働省:「身体活動とエネルギー・栄養素について」
したがって、毎日500キロカロリーずつ減らせば、約2週間で1kg痩せる計算です。
消費カロリーは「貯金を使うこと」に似ており、食べたエネルギーだけでは足りなくなると、貯金(=体脂肪)を取り崩して補います。
これを続けると、脂肪が減って体重が軽くなります。

運動をしてカロリーを消費したり、食べる量をコントロールすることで、健康的にダイエットを進めることができるので、ぜひ記録することを習慣化していきましょう。
自分の適正体重を知るには、「BMI(ボディ・マス・インデックス)」と「標準体重」を計算すると良いです。
BMIとは、身長と体重のバランスを表す数値で、計算式は以下の通りです。
BMI=体重(kg)÷(身長(m)×身長(m))
例えば、身長160cm(1.6m)、体重60kgの場合: 60kg ÷ (1.6m × 1.6m) = 23.4(BMI)
BMIの目安は以下の通りです。
| BMI値 | 判定 |
|---|---|
| 18.5未満 | やせすぎ |
| 18.5~24.9 | 標準体重 |
| 25.0以上 | 肥満 |
また、標準体重の計算方法は以下の通りです。
標準体重=身長(m)×身長(m)×22
例えば、160cm(1.6m)の場合: 1.6m × 1.6m × 22 = 56.3kg
BMIは「学校の成績表」に似ています。適正な範囲にいるかどうかを数字で確認できるので、自分に合った目標を立てるのに役立ちます。

ダイエットの目標を決める前に、自分のBMIと標準体重を計算し、無理のない範囲でカロリー設定を進めましょう。
ダイエットを成功させるためには、1日にどれくらいのカロリーを摂取すればいいのかを知ることが大切です。
摂取カロリーを適切に管理することで、健康的に体重をコントロールできます。
本記事では、「基礎代謝量」「1日の消費カロリー」「年齢や性別ごとの摂取カロリーの目安」「ダイエット中の適切な摂取カロリー設定方法」について、わかりやすく解説します。
基礎代謝量とは、何もしなくても消費されるエネルギーのことです。これを知ることで、最低限必要なカロリーを把握できます。
基礎代謝量は、年齢・性別・体重によって異なります。一般的な計算方法は以下の通りです(ハリス・ベネディクト方程式)。
男性:66 + (13.7 × 体重kg) + (5.0 × 身長cm) – (6.8 × 年齢)=基礎代謝量
女性:655 + (9.6 × 体重kg) + (1.8 × 身長cm) – (4.7 × 年齢)=基礎代謝量
基礎代謝は「家の電気代」のようなもの。何もしなくても使う電気代があるのと同じで、体もじっとしていてもエネルギーを消費します。

基礎代謝量を知ることで、無理なくカロリーを管理するための基準ができるでしょう。
1日の消費カロリーは、基礎代謝量に運動や日常活動のエネルギー消費を加えたものです。
総消費カロリーは「基礎代謝量 × 活動レベル」で求めます。活動レベルは以下の通りです。
| 低活動(デスクワーク中心) | 基礎代謝量 × 1.2 |
| 普通(軽い運動をする) | 基礎代謝量 × 1.55 |
| 高活動(運動習慣がある) | 基礎代謝量 × 1.75 |
消費カロリーは「スマホのバッテリー消費」に似ています。何もしていなくても電池は減りますが、たくさん使うほど早く減るのと同じです。
1日の消費カロリーを知ることで、食事と運動のバランスを考えやすくなります。
年齢や性別によって、適切な摂取カロリーは異なります。以下の表を参考に、自分に合ったカロリーを確認しましょう。
| 年齢 | 男性(約kcal) | 女性(約kcal) |
|---|---|---|
| 10代 | 2,600 | 2,100 |
| 20代 | 2,700 | 2,000 |
| 30代 | 2,600 | 2,000 |
| 40代 | 2,400 | 1,900 |
| 50代 | 2,200 | 1,700 |
厚生労働省のデータによると、活動量が少ない人ほど摂取カロリーを抑える必要があります。
また、以下のグラフを見ても明らかですが、活動時間が少ない人ほど死亡リスクや生活習慣病のリスクが顕著に現れているため、週に一回でもいいので軽い運動をしてみてください。
引用:厚生労働省:「健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023」
その他の研究でも示されていますが(reason)週に1回の運動でも健康面での効果があることが確認されています。※3引用:NCBI:「週末の余暇時間の身体活動と日本人男性の2型糖尿病リスク:大阪健康調査」
摂取カロリーは「車の燃費」に似ています。
走行距離が長い(=活動量が多い)ほど、たくさんの燃料(=カロリー)が必要になります。

年齢や生活習慣に合ったカロリーを摂取することが、健康維持のカギとなることを確認しておきましょう。
ダイエット中は「消費カロリーより摂取カロリーを少なくする」ことが重要です。
脂肪1kgを減らすには約7,000キロカロリーの消費が必要です。そのため、1日500キロカロリーを減らせば、約2週間で1kgの脂肪を減らせます。
1.1日の消費カロリーを求める
2.目標に応じて以下のカロリーを差し引く
L2-1.緩やかに減量(1か月で約2kg):-500kcal/日
L2-2.やや早く減量(1か月で約4kg):-750kcal/日
ダイエットは「お金の節約」に似ています。毎日少しずつ節約(=摂取カロリーを減らす)すれば、貯金(=脂肪)が減っていきます。

無理のない範囲で目標摂取カロリーを設定し、健康的にダイエットを進めましょう。
健康的な体を維持するためには、1日に摂取するカロリーバランスが大切です。
多すぎると太ってしまい、逆に少なすぎても体に悪影響を与えることがあります。
先ほどお見せした以下のグラフでも、過剰摂取や一切栄養素を取らないことによる悪影響については自明となっています。
引用:厚生労働省:「健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023」
また、自分の目標体重や基礎代謝量を知ることで、適切なカロリー管理が可能になります。
本記事では、摂取カロリーの適正な範囲とその理由についてわかりやすく解説します。
食べすぎると、体に必要以上のエネルギーが蓄積され、体重が増えてしまいます。
食べ物から得たエネルギー(カロリー)が、1日に使うエネルギーを超えると、余った分は脂肪として体に蓄えられます。
前述したとおりですが、厚生労働省の報告書によると、成人女性の推奨摂取カロリーは約1,800~2,200kcal、成人男性は約2,200~2,600kcalです。
それよりも多くのカロリーを摂取してしまうと一般的には、体重が増えてしまうことになるでしょう。
カロリーは「おこづかい」のようなものです。もらったおこづかいを全部使わずに貯め続けると、どんどんお金(=脂肪)が増えてしまうのと同じです。
摂取カロリーを適切にコントロールしないと、脂肪が増えすぎて太ってしまいます。
食事を極端に減らしすぎると、逆に太りやすい体になってしまいます。
食事の量を極端に減らすと、体は「エネルギー不足」と判断し、少ないエネルギーで動こうとします。
その結果、代謝が落ちエネルギーをあまり消費しなくなるため、ちょっと食べただけでも太りやすくなってしまうような体型へと進んでいくのです。
カロリーを極端に減らすのは、「節水モードのシャワー」に似ています。
水が少なくても使えるように調整されるのと同じで、体も少ないカロリーで動けるようになってしまい、エネルギーを消費しにくくなります。

健康的に痩せるには、適度なカロリー摂取を維持しながら、無理のない範囲で運動を行うことが大切です。
ダイエットを成功させるには、計画的な準備が大切であり、目標を決めずに始めると、途中で挫折しやすくなります。
まずは「目標体重の設定」「基礎代謝量の把握」「1日の消費カロリー計算」「食事の見直し」「目標体重までのカロリー管理」を行い、効率よく健康的に痩せる準備をしましょう。
ダイエットの第一歩は、自分の目標体重を決めることです。
目標体重を決めることで、どれくらいの期間でどれだけ痩せる必要があるのかが明確になります。
逆に目標があいまいだと、途中でやる気を失いやすくなってしまうでしょう。
目標体重を決めるのは「旅行の目的地を決めること」に似ています。
行き先が決まっていないと、どの道を通るべきかどの通行手段を使えばいいのかわからず迷ってしまいますよね。
明確な目標を設定することで、ダイエットの計画を立てやすくなります。
自分が1日にどれくらいのカロリーを消費しているのかを知ることも重要です。
前述した計算式で基礎代謝を算出した上で消費カロリーも出していきましょう。
消費カロリーは、基礎代謝量に日常生活や運動で消費するエネルギーを加えたものです。

こちらも改めて以下に計算式を記載しておきますね。
| 低活動(デスクワーク中心) | 基礎代謝量 × 1.2 |
| 普通(軽い運動をする) | 基礎代謝量 × 1.55 |
| 高活動(運動習慣がある) | 基礎代謝量 × 1.75 |
消費カロリーは「スマホのバッテリー消費」に似ています。何もしていなくてもバッテリーは減りますが、動画をたくさん見ると早く減るのと同じです。
1日の消費カロリーを知ることで、適切なカロリー管理ができます。
食事を見直すことで、健康的にダイエットを進めることができます。
バランスの良い食事をとることで、無理なくカロリーを抑えながら栄養をしっかり摂ることができます。
- 高カロリー食品を控える(揚げ物・甘い飲み物など)
- 野菜やタンパク質を増やす(筋肉を維持しながら痩せやすい体に)
- 食事の回数を適切にする(1日3食を意識し、間食を減らす)
食事の見直しは「車の燃料選び」に似ています。
質の良い燃料を入れると、車がスムーズに動くように、体も適切な食事をとることで健康的に動けます。
栄養バランスの取れた食事はメンタル改善効果や美肌効果も現れるため、美容面でも効果的な取り組みです。
食事の栄養バランスを考えながら、適切なカロリー摂取を心がけましょう。
目標体重までにどれだけカロリーを消費する必要があるのかを計算しましょう。
脂肪1kgを減らすには約7,000~7,200kcalの消費が必要です。
例えば、1日500kcalを消費すれば約2週間で1kg痩せる計算になります。
- 目標体重を決める
- 現在の体重との差を出す
- 1kg減らすのに必要なカロリー(7,200kcal)をかける
無理なく続けられる範囲でカロリー管理を行い、健康的に目標体重を達成しましょう。
ダイエットを成功させるには、計画的に取り組むことが大切です。
摂取カロリーを管理し、栄養バランスを考えながら食事をとることで、健康的に体重を減らせます。
それに加えて、運動や食事制限を適切に取り入れることで、リバウンドを防ぎながら理想の体型を目指せます。
本記事では、具体的なステップを紹介します。
ダイエットでは、摂取カロリーを適切に管理しながら食事をとることが重要です。
消費カロリーより摂取カロリーが多いと太り、少ないと痩せます。
1日の適正摂取カロリーは、基礎代謝量と運動量を考慮して決めます。
基礎代謝量や消費カロリーに関しては前述した計算式を参照の上、算出してみてください。
たんぱく質(P)、脂質(F)、炭水化物(C)のバランスを考えて食事をしましょう。
PFCバランスは、健康的に痩せるための基本です。以下の計算基準を1つの目安にしてください。
- たんぱく質:体重×1.2~1.6g
- 脂質:総摂取カロリーの20~30%
- 炭水化物:残りのカロリー
PFCバランスは「給食の献立」に似ています。おかずばかりでも、ご飯ばかりでも栄養が偏るため、適切なバランスが必要です。
PFCバランスを意識することで、筋肉を維持しながら健康的に痩せられます。
食事だけでなく、運動も取り入れるとダイエットが成功しやすくなります。
運動をすると消費カロリーが増え、脂肪が燃えやすくなり、ウォーキングや筋トレを組み合わせると効果的です。
運動は「車のエンジンを動かす」ことと同じです。
走ることで燃料(脂肪)が消費されるように、運動をするとエネルギーが使われます。

適度な運動を取り入れると、健康的にダイエットを進められるでしょう。
糖質を適度に制限すると、効率よく体脂肪を減らせます。
糖質を減らすと、脂肪がエネルギーとして使われやすくなります。目安は1日130g程度ですが、極端な制限は健康に悪影響を及ぼすので注意してください。
ケトジェニックダイエットを行う場合、糖質を1日に20g~40g以下に制限し続けます。
詳しくは以下の記事で解説していますので、ご確認ください。
脂質の摂取量を適切に管理することで、ダイエットを効率よく進められます。
脂質は他の栄養素と比較してカロリーが高いため、過剰摂取すると太りやすくなっていくでしょう。
1日の脂質摂取量は総カロリーの20~30%が目安です。

女性は肌の艶も維持しながらダイエットしていけるのが理想なので、一切の脂質を摂取しないという選択肢は厳禁です。
適度な脂質制限をすることで、健康的にダイエットができます。
食事の時間を工夫することで、ダイエット効果を高められます。
夜遅くに食べると、脂肪が蓄積されやすくなります。理想は、以下の間隔で食事をすることです。
- 朝食:7~9時
- 昼食:12~14時
- 間食:16~17時
- 夕食:18~20時
食事を摂る時間を固定することで、体内のリズムを整えてダイエットに適した生活習慣を体が勝手に作ってくれます。
適切な時間に食事をとることで、脂肪の蓄積をも防ぎやすくなるでしょう。
ダイエットを成功させるには、ただ体重を減らすだけではなく、健康を保ちながら続けることが大切です。
無理な食事制限や極端なダイエットは、体調を崩したり、リバウンドの原因になってしまうでしょう。
安全で効果的なダイエットをするために、気をつけるべきポイントを紹介します。
ダイエット中でも栄養をしっかり摂らないと、体調を崩してしまいます。
食事の量を極端に減らすと、体に必要なビタミンやミネラルが不足し、貧血やめまい含めた免疫力の低下につながることがあります。
厚生労働省によると、特に鉄分やカルシウムが不足しやすく、健康への影響が大きいとされています。
以下に、鉄分とカルシウムの推奨摂取量を記載しておきます。
鉄分の推奨摂取基準
| 年齢 | 男性 基本的鉄損失(mg)^2 | 女性 基本的鉄損失(mg)^2 |
|---|---|---|
| 18~29歳 | 0.90 | 0.77 |
| 30~49歳 | 0.97 | 0.79 |
| 50~64歳 | 0.96 | 0.80 |
| 65~74歳 | 0.92 | 0.79 |
カルシウムの食品摂取基準
| 年齢 | 男性 推奨量(mg/日) | 女性 推奨量(mg/日) |
|---|---|---|
| 18~29歳 | 800 | 650 |
| 30~49歳 | 750 | 650 |
| 50~64歳 | 750 | 650 |
| 65~74歳 | 750 | 650 |
栄養不足は「ガソリンが足りない車」のようなものです。燃料がなければ、車が動かないのと同じで、体もエネルギー不足で動きにくくなります。

バランスの良い食事を意識しながら、必要な栄養をしっかり摂りましょう。
無理な食事制限をすると、脂肪だけでなく筋肉も減ってしまいます。
なぜなら、食事の量を減らしすぎると体はエネルギー不足を補うために筋肉を分解して不足分のエネルギーを生成していくからです。
それにより、筋肉が減ると代謝が下がり、太りやすく痩せにくい体を作ることに繋がってしまいます。
筋肉は「家の柱」のようなものです。柱が弱いと家全体が不安定になるように、筋肉が減ると体が弱くなり、リバウンドしやすくなります。

タンパク質をしっかり摂りながら、適度な運動を取り入れることが大切です。
急激なダイエットをすると、リバウンドしやすくなります。
短期間で急激に体重を落とすと、体は飢餓状態だと判断し、エネルギーをできるだけ蓄えようとします。
その結果、ダイエットをやめた途端に体重が戻りやすくなります。
リバウンドは「ゴムを引っ張る」ようなものです。強く引っ張ると、手を離したときに勢いよく戻るのと同じで、急激なダイエットは体重が元に戻りやすいのです。

無理のないペースで体重を減らし、長く続けられる方法を選びましょう!
健康的に痩せるには、1ヶ月で体重の5%以内の減量が目安です。
急激に体重を落とすと、筋肉の減少や体調不良の原因になります。厚生労働省の指標では、1週間に0.5~1kgの減量が安全とされています。(reason)
reason:厚生労働省:「健康的な体づくりのための生活習慣見直しノート」
ダイエットは「ゆっくり進む電車」のようなものです。急ブレーキをかけると危険なように、急激な体重減少は体に負担をかけます。
長期的な目標を立て、ゆっくりと確実に体重を減らしましょう。
食事の回数や時間を適切に管理することで、ダイエットの効果を高められます。
長時間空腹のままでいると、次の食事で血糖値が急上昇し、脂肪が蓄積しやすくなります。また、夜遅くの食事は消費しきれずに脂肪として蓄えられやすくなります。
食事の管理は「定期的な電車の運行」に似ています。適切な時間に運行することで、スムーズに移動できるのと同じように、規則正しい食事で体のリズムを整えられます。

プチ断食を局所的に実施するのもおすすめです。
ですが、1日3食を基本のベースにし、夜遅くの食事は避けるようにしましょう。
カロリー計算は大事ですが、神経質になりすぎるとストレスになります。
カロリーばかり気にしすぎると、食事を楽しめなくなり、ダイエットが続かなくなってしまうでしょう。
つまり、比較的ざっくりと全体の摂取カロリーを把握しながら、無理のない範囲で調整することが大切です。
カロリー計算は「家計管理」に似ています。毎日細かく計算しすぎると疲れてしまうので、大まかに収支を把握するのが長続きするコツです。

適度にカロリーを意識しながら、ストレスのない範囲でダイエットを続けましょう。
ダイエットが成功した後も、体重を維持し、健康的な生活を続けることが大切です。
リバウンドを防ぎ、理想の体型をキープするためには、定期的な体重管理や生活習慣の見直しが必要になります。
本記事では、ダイエット後に意識するべきポイントを紹介します。
ダイエット後も、週ごとに体重をチェックしながら変化を意識することが大切です。
ダイエットが終わると、食生活が緩みやすくなります。
体重の増減を把握することで、無意識のうちにリバウンドしてしまうのを防ぐことができるでしょう。
厚生労働省のデータによると、体重を定期的に管理する人の方が、体重を維持しやすいとされています。
体重管理は「貯金の残高確認」に似ています。こまめにチェックすれば、無駄遣い(食べ過ぎ)を防げますが、長期間放置すると、知らないうちにお金が減ってしまう(体重が増える)ことがあります。

週に1回は体重を測り、増えていたら食生活や運動習慣を見直すようにしましょう。
ダイエットが終わった後も、健康を維持するために生活習慣を見直すことが大切です。
体重が減ったからといって、以前の食生活に戻るとリバウンドしてしまいます。適度な運動やバランスの良い食事を続けることで、理想の体型を維持しやすくなるでしょう。
- 食事:栄養バランスを考え、過度な食べ過ぎを防ぐ
- 運動:ウォーキングや筋トレを週2~3回続ける
- 睡眠:しっかり寝ることで、食欲のコントロールがしやすくなる
健康維持は「歯磨き」に似ています。毎日少しずつ続けることで、虫歯(リバウンド)を防げるように、日々の積み重ねが大切です。
ダイエット後も健康を意識し、良い習慣を続けることで、無理なく理想の体型を維持できます。
ダイエットをしていると、「なぜ体重が減らないの?」「運動しなくても痩せるの?」など、疑問がたくさん出てきます。間違った方法で努力が無駄にならないように、よくある質問にわかりやすく答えます。ダイエットを成功させるための正しい知識を身につけましょう。
- 摂取カロリーを減らしても体重が減らないのはなぜですか?
- 多くの場合、以下のケースに当てはまっている場合があります。
定期的に運動が行えているのか、無意識下で食べている食事等はないか振り返ってみてください。
1.基礎代謝の低下:食事を減らしすぎると、体が省エネモードになり、エネルギー消費が少なくなります。
2.水分やむくみ:体は水分を溜め込みやすく、特に塩分が多い食事をするとむくみが起こります。
3.筋肉量の減少:無理な食事制限で筋肉が減ると、代謝が落ちて痩せにくくなります。
- 運動なしのカロリー制限だけでダイエットはできますか?
- 結論、可能です。
しかしながら、リバウンドしやすいリスクがあるため、長期的に続けていける方法なのであれば、食事だけでも問題ないかと思われます。
以下に、なぜカロリー制限だけだとリバウンドしやすいのか記載しておきますので、確認してみてください。
1.筋肉が減る:運動をしないと筋肉量が減り、代謝が落ちてしまいます。
2.痩せにくくなる:代謝が低下すると、同じカロリーを摂っていても太りやすくなります。
3.リバウンドのリスク:筋肉が減ると、少し食べただけで体重が戻りやすくなります。
- 生理中はどうやってカロリー調整すればいいですか?
- 結論、生理中であればあるほどカロリーはしっかり摂取してください。
以下に、理由を記載しておきます。
1.鉄分が不足しやすい:生理中は鉄分が失われるため、貧血を防ぐために摂取が必要です。
2.食欲が増えやすい:ホルモンの影響で食欲が増すため、バランスの良い食事が大切です。
3.むくみやすい:塩分を控えめにすると、むくみを防げます。
その上でおすすめの食材・栄養素は以下です。
1.鉄分が多いもの(レバー、ほうれん草)
2.タンパク質(豆腐、鶏肉、魚)
3.ビタミンB群(玄米、バナナ)
- ダイエットサプリや漢方を取り入れるのは効果的ですか?
- 結論、サプリのみで痩せることは難しいです。
食事と運動からアプローチをしていくのが確実と言えます。
以下に、なぜサプリ・漢方のみがおすすめできないのかの理由を記載しておきます。
1.即効性はない:どんなサプリや漢方でも、食事や運動なしで効果を出すのは難しいです。
2.体質によって合う・合わないがある:人によって効果が違い、すべての人に合うわけではありません。
3.食事と運動が基本:ダイエットの基本は、バランスの取れた食事と適度な運動です。

自分の体に合った摂取カロリーを知り、適切な栄養バランスを保ちながら、無理なく健康的に体重を減らしていくのが本来のダイエットであり、理想像と言えます。
カロリー計算は最初こそ少し面倒に感じるかもしれませんが、続けていくうちに習慣になり、自然とダイエットが楽に感じるようになります。
重要なのは、自分に合った目標を設定し継続すること。少しずつの積み重ねが大きな成果を生むのです。

最後に、ダイエットは焦らず、楽しみながら続けることが大切です。
今すぐにでも始められるシンプルな方法を実践して、あなたの理想の体型に向けて一歩踏み出してみましょう!




